出雲大社のタブー7選!本殿にはは入れない?おすすめの参拝ルートも紹介
出雲大社には参拝時のタブーがあることを知っていましたか?この記事では、出雲大社のタブー7つを紹介します。出雲大社のおすすめ参拝ルートや本殿に入れない理由、行ってはいけない日も紹介するので参考にしてください。
目次
出雲大社は有名なパワースポット!

出雲大社は島根県出雲市にある神社で、年間数百万人以上が参拝に訪れている有名なパワースポットです。創建の時期は不明ですが、国内最古の歴史書と呼ばれる古事記にも記載されています。古くより「神が集まる場所」として知られ、大切にされてました。
祀られているのは、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)。七福神の大黒天とは別の神様ですが、因幡の白兎という物語に登場する神様で、白兎を助けた「だいこく様」として親しまれています。
主に縁結びの神として知られていますが、この「縁」とは恋愛における縁に限らず、全ての人間が共に発展していくための尊い「縁」とされていますよ。他にも、子授かりや商売繁盛などのご利益もあります。以下ではそんな出雲大社のタブーを中心に紹介していきますね。
| 電話番号 | 0853-53-3100 |
|---|---|
| 住所 | 島根県出雲市大社町杵築東195 |
| 公式HP | https://izumooyashiro.or.jp/ |
| 営業時間 | 6:00~19:00 |
出雲大社のタブー・やってはいけないことは?
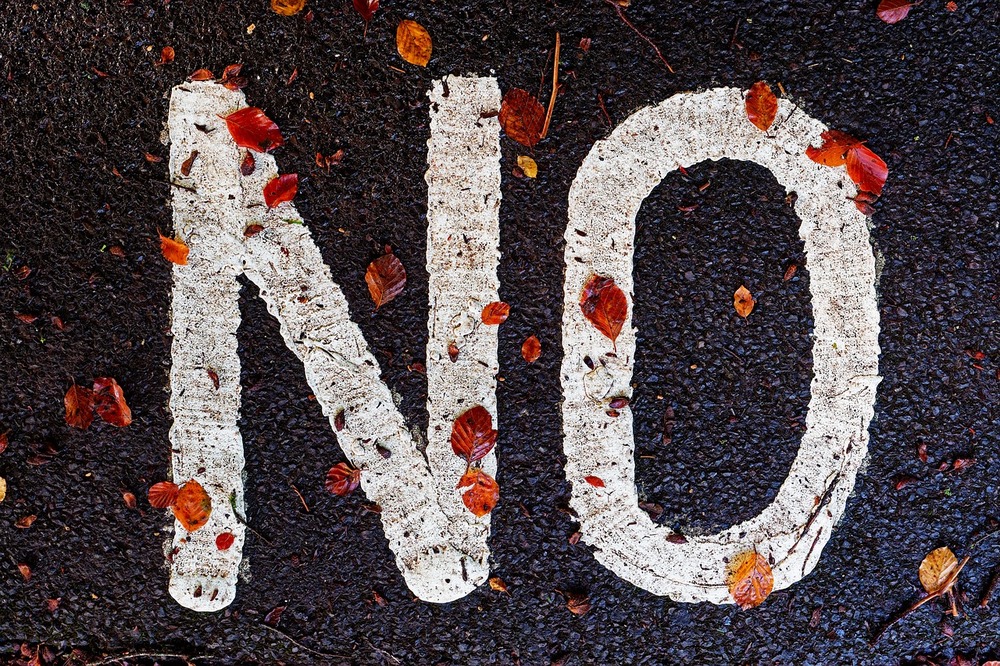
日本の歴史に深く関わり、国宝にも指定されている出雲大社ですが、参拝時にやってはいけないことがあるのをご存知でしょうか?ここからは出雲大社のタブーややってはいけないことについて紹介します。ぜひ参拝に行く際の参考にしてくださいね。
①過度にラフな格好で参拝すること
出雲大社に限らず神社に行くときは、ラフな服装を避けましょう。神社は神聖な場所であり、神様のおうちです。敬意を持つ相手の家にだらしない格好では訪問しませんよね。ラフすぎる服装は、神社においてタブーとされます。具体的にNGな服装の例は以下の通りです。
- ラフすぎる服
- 露出度が高すぎる服
- しわやほつれが目立つ服
タブーとなるラフすぎるファッションは、サンダルやジャージ、スウェットやタンクトップなどがあげられます。露出度が高い服は、ミニスカートやショートパンツなどです。正装である必要はありませんが、誰に見られても恥ずかしくないTPOを考えた服装で参拝しましょう。
出雲大社を参拝する際に避けたいダメな服装については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。
②お清めの砂を勝手に持ち帰ること
出雲大社にある「お清めの砂」は、勝手に持ち帰ってはいけません。お清めの砂とは、出雲大社にある素鵞社(そがのやしろ)」社殿の床縁下に敷き詰められている砂のことです。御砂とも呼ばれています。
出雲大社では、この砂を持って帰るという習慣があります。厄払いやお守り、お清めの効果があるとされているためです。家や田畑に巻いて、神様の加護を受けるために使います。しかし、お清めの砂を持ち帰るには正しい手順を踏む必要がありますよ。
これは、ただいただいて帰るだけではいけません。まず、日本海に臨む稲佐の浜(出雲大社より西へ約800メートル)の浜辺の砂を掻き採って素鵞社をお参りし、稲佐の浜で搔き採ってきたその砂を床縁下に置き供え、そして、従来からある御砂をいただいて帰るというものです。
お清めの砂を持ち帰りたい人は、勝手に持ち帰るのではなく、上記の手順を参考にして稲佐の浜と交換しましょう。正しく持ち帰った御砂を自宅の敷地などに撒けば、ご利益があるかもしれませんよ。
ヒーラー育成講師 野村香織
稲佐の浜は出雲大社から車で3分、徒歩15分程です。
神無月の10月は出雲に神様が集まるので、出雲では神在月と呼ばれています。
その際、稲佐の浜で神様をお迎えする神迎神事が行われます。
③お賽銭を乱暴に投げ込むこと
お賽銭箱にお金を放り投げるイメージが強いお賽銭ですが、乱暴に投げ入れるのはタブーです。出雲大社でお賽銭をするときは、音を立てないように丁寧にそっと入れましょう。また、お賽銭はのし袋や半紙に包んであるとより丁寧な印象を与えます。
お賽銭は、願い事を叶えてくれたお礼として神様にお供えするお金です。混んでいて遠くから投げざるをえない場合も、力任せに投げるのではなく、神様に感謝の気持ちが届くように心を込めて優しく投げ入れてくださいね。
神様への捧げ物なのですから、お賽銭を高いところから落とすように投げ込むのもタブーです。腰元の高さから下から上へ、静かに入れるようにしましょう。
④参道の中央を歩くこと
出雲大社だけでなく、どの神社でも参道の中央を歩くのはタブーです。参道の中央は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様の通り道とされているためですね。参道は基本的に端を歩くようにしましょう。
中央を横切る場合でも、頭を下げてから通るのが作法とされています。神職の方がそうされていますので、気になる方は観察してみてください。
また、出雲大社では参道の左側から入り、帰る時はその逆を通る方が良いとされています。常に左側通行をするイメージです。
混雑しているときや友人と横一列で歩いているときなどは、無意識に中央に流されてしまいがちなので、気を付けるようにしましょう。
⑤「二礼二拍手一礼」をすること
神社での参拝といえば、二回礼をして二回拍手、最後に一礼の「二礼二拍手一礼」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし出雲大社では、二回礼をして四回拍手、最後に一礼の「二礼四拍手一礼」が正しい参拝作法となります。
四拍手をする意味としては「春夏秋冬を表し、天災が降りかからず、繁栄し続けることを祈願する」という意味や「東西南北を表現し、四方八方を護る神様に敬意を表す」という説があります。
一般的には「2礼2拍手1礼」ですが、出雲大社の正式な参拝作法は「2礼4拍手1礼」となります。ご本殿以外のご社殿をお参りの際にも、この作法にてご参拝下さい。 4拍手をする理由ですが、当社で最も大きな祭典は5月14日の例祭(勅祭)で、この時には8拍手をいたします。数字の「8」は古くより無限の数を意味する数字で、8拍手は神様に対し限りない拍手をもってお讃えする作法です。ただし、8拍手は年に1度の例祭(勅祭)の時のみの作法としています。平素、日常的には半分の4拍手で神様をお讃えする4拍手の作法としていますが、お祈りお讃えするお心に差はありません。
出雲大社の公式ホームページでも、上記のように作法として二礼四拍手一礼を推奨しています。出雲大社内の拝殿や祠などに参拝する際は、2回礼をした後に4回手を叩いて再度一礼しましょう。
⑥おみくじを境内の木に結ぶこと
出雲大社で引いたおみくじを境内の木に結ぶのはタブーです。おみくじを引いた後は、大切に持って帰るか決められた場所に結びましょう。ちなみに出雲大社のおみくじは、敷地内にある御守所で引くことができます。
出雲大社をはじめ、神道では、どんなものにも神が宿るとされています。それはもちろん、境内にある木も同じです。おみくじを結ぶことで枝が傷んだり、結ぶ人に根を踏まれ木が弱る可能性があります。神を傷つける行為になるということを忘れないでくださいね。
特に出雲大社には推定樹齢1000年といわれるむく木の御神木をはじめ、貴重な樹木があります。長い歴史の中で大切にされてきた樹木を、おみくじを結ぶことで傷つけてしまっては大変です。「たかが木」と軽んじることなく、大切に扱いましょうね。
出雲大社の敷地内にも、おみくじを結ぶための場所はあります。おみくじを引いた後のマナーにも気を配りましょう。ちなみに、持ち帰ったおみくじを処分する場合は、古いお守りやお札と同じように近くの神社へ返納してお焚き上げしてもらうと良いですよ。
⑦宇迦橋(うがばし)の大鳥居を通らずに参拝すること
出雲大社を参拝する際は、必ず宇迦橋(うがばし)の大鳥居を通ってから参拝しましょう。出雲大社には御本殿に辿り着くまでに、石や鉄などそれぞれ違う素材でできた鳥居が四つあります。
宇迦橋(うがばし)の大鳥居はコンクリート製の大きな鳥居です。大正天皇の即位をお祝いして建てられました。
境内から少し離れているため見落とされがちですが、神門通りにある宇迦橋の大鳥居が「一の鳥居」です。そこから順に勢溜の鳥居、松の参道の鳥居、銅の鳥居をくぐって参拝してくださいね。
出雲神社の本殿には入れない?理由は?
出雲大社の本殿には入ることができません。出雲大社では、日本神話の伝え話により出雲国造家(いずものくにのみやつこ)のみが、祭祀を主宰することが許されています。そのため、天皇であっても本殿に入ることはタブー視され、歴史上一度もできていないのです。
出雲国造家は、天照大神(あまてらすおおみかみ)の子の天穂日命(あめのほひのみこと)を祖先とした古代出雲の豪族。現在は、千家氏と北島氏の二氏が出雲国造として祭祀を担っています。
ちなみに、出雲大社の本殿に入れる出雲国造であったとしても、入る際には服装について厳しく定められています。さらに、出雲大社の本殿は撮影禁止です。それだけ出雲大社の本殿は神聖で、謎に包まれた場所だと言えるでしょう。
なお、2013年に行われた60年に一度の大遷宮で、一時的に本殿が一般開放されたことはあります。
出雲大社のおすすめ参拝ルートは?
ここからは出雲大社のおすすめ参拝ルートを紹介します。合わせて見どころやタブー、手水舎での作法などについてもまとめていますので、参考にしてくださいね。
①鳥居をくぐって境内へ
まずは鳥居をくぐって境内に入りましょう。先に一の鳥居をくぐって敷地内に入ったら、次は二の鳥居です。
境内に近い二の鳥居は、「勢溜(せいだまり)の大鳥居」と呼ばれていますよ。勢溜と呼ばれているのは、ここが人が集まる場所であるため。江戸時代には見せ物小屋が多数あり、賑わっていたといわれています。
この鳥居は元々木造でしたが、2018年に建て替えられ、現在は耐候性に優れた鋼鉄製です。8メートル以上の高さを誇っています。鳥居に一礼し、向かって左側から静かに入っていきましょう。
②祓社で身を清める
参道に入ると、右側に祓社(はらえのやしろ)という祓戸神(はらいどのかみ)の祠があります。
祓戸神は、瀬織津比咩神(せおりつひめのかみ)、速開都比咩神(はやあきつひめのかみ)、気吹戸主神(いぶきどぬしのかみ)、速佐須良比咩神(はやさすらひめのかみ)という4柱の神様を総称したものです。人が気が付かぬ間に犯した罪や穢れを祓ってくださいます。
拝殿にお参りする前には、必ず立ち寄ってお参りし、身を清めましょう。また、梅雨時期には周囲に紫陽花が咲き誇り、美しい姿を眺めることもできます。タイミングを合わせて足を運んでみるのも良いですね。
ヒーラー育成講師 野村香織
出雲大社のように祓社のある神社は多くあります。
(奈良の大神神社、春日大社など)
鳥居をくぐってすぐや、御本殿の手前に祀られていることがありますので、必ずそちらにご挨拶をして自身の穢れを祓い落としてから向かいましょう。
③松の参道
身を清め終わったら、日本名松100選に入る見た目も美しい「松の参道」を通りましょう。松の参道も鳥居と同じで真ん中は神様のための道ですので、左端から歩くよう注意してくださいね。
松の参道の中には、三の鳥居もあります。周囲に木があるため見逃してしまいがちですが、こちらも忘れず通っておきましょう。
出雲大社にある松の山道は江戸時代前期に整備が開始されたと考えられています。推定樹齢350年以上の古い木もありますので、歴史を感じながらゆっくりと散策するのがおすすめですよ。
④御神像
境内の手前には、2つの御神像があります。左側が「御慈愛の御神像」で、右側が大国主大神をかたどった「ムスビの御神像」です。
この像は海の彼方からやってくる幸魂(さきみたま)・奇魂(くしみたま)を発見し、大国主大神が神様として目覚めた瞬間を表現しています。
幸魂は、人に幸せを与える霊魂で、奇魂は不思議なパワーで物事を成就させる力を持つ霊魂です。大国主大神はこの2つの魂によって自分が生かされたことに気がついたことで、神性を養ったといわれています。
芸術品としても価値の高い像です。周囲を散策しながらじっくり眺めてみましょう。
⑤手水舎で手と口を清める
続いて、手水舎で手と口を清めましょう。手水舎は四の鳥居である銅鳥居の近くにあります。清め方の手順は以下の通りで、一般的な神社と変わりありません。
1.右手に柄杓を持ち、水を流して左手を洗い清める
2.左手に柄杓を持ち替え、水を流して右手を洗い清める
3.右手に水を汲み口を濯いで清める
4.右手に柄杓を持ち替え、左手を再び洗う
5.柄杓を立てて、持っていた部分に水を流して清める
6.柄杓を元の場所に戻す
口を洗う際に、柄杓を直接口につけるのはタブーです。必ず水は手にとってから、口を濯ぐようにしましょう。また、口から水を流すときには口元を覆う、迷惑のかからない場所に流すなどマナーを守って行いましょうね。
銅鳥居を潜ると、ここから先は神の領域である「荒垣」に入ります。神様に失礼のないよう、しっかりと手や口を清めておきましょう。
⑥銅鳥居をくぐる
続いて、国の重要文化財となっている銅鳥居をくぐりましょう。銅鳥居は四の鳥居にあたるため、こちらで出雲大社の鳥居は最後とのなります。
銅鳥居は青銅製で、1666年に毛利網広によって出雲大社に寄付されたものです。ちなみに、毛利網広は、三本の矢でお馴染みの毛利元就の孫である毛利輝元のさらに孫にあたります。
銅鳥居は、現在の山口県萩市にあたる場所で毛利藩の鋳物師が作ったと伝えられていますよ。ここをくぐれば、拝殿はもう目の前です。神様に挨拶をするつもりで心を込めて一礼し、静かな心で神域に入りましょう。
⑦拝殿に参拝する
鳥居をくぐったら、その先にある拝殿に参拝します。拝殿は、行事やご祈祷が行われる場所です。ここは神域ですので、一層マナーに気をつけましょう。神様に感謝し、謙虚な気持ちで足を運んでくださいね。
ちなみに、出雲大社の拝殿は、昭和28年の火災で焼けてしまったものを復元したものです。とはいえ、建築物として価値があります。
当時の神社建築学の権威であった人物が設計し、大社造と切妻造の折衷様式がで作られているためです。また、しめ縄が他の神社と左右逆で締められていることも、注目のポイント。出雲大社では大昔から、左が上位で右が下位と決められていたからです。
二礼四拍手一礼で神様にご挨拶をし、歴史と文化が感じられる建物をじっくり観察して回ると良いでしょう。
⑧八足門から御本殿を参拝する
最後に八足門から御本殿を参拝します。出雲大社では、一般の参拝客が御本殿まで入ることができません。そのため、八足門から参拝する形になります。御本殿は檜皮葺屋根を持つ大社造りの建物で、荘厳な雰囲気があります。
先ほど説明した通り、出雲大社の本殿はとても神聖な建物なので、ごく一部の人しか入ることができません。門から眺めるだけになってしまいますが、厳かな気持ちで手を合わせましょう。
なお、八足門から御本殿までには楼門があります。こちらも通常は入れませんが、特別に八足門から楼門まで入ることができる機会がもうけられていることがあります。気になる方は情報を確認し、足を運んでみましょう。
出雲大社に入ってはいけない日がある?

出雲大社には、入ってはいけない日があります。具体的にはどんな日なのでしょうか?以下で紹介します。失礼のないよう出雲大社に参拝するためにも、ポイントを押さえてくださいね。
忌中
忌中の間は、出雲大社に入ってはいけません。忌中とは、いわゆる四十九日の法要が終了するまでの期間を指します。神葬祭の場合は、五十日祭が終わるまでの期間が忌中の扱いです。忌中は死の穢れを払い、亡くなった方の冥福を祈る期間とされています。
一般的に、忌中には贈り物やお祝いをしてはいけません。旅行やレジャーも推奨されません。死の穢れを神聖な場所に持ち込むことにつながりますから、出雲大社に限らず、神社に行くことも避けましょう。
人が亡くなって辛いタイミングではありますが、神様に縋るのではなく、個人との別れを惜しむ大切な時間にしてくださいね。
縁起の悪い日
「縁起の悪い日」として有名な日も、出雲大社に入ってはいけません。縁起の悪い日に行くのはタブーとされるだけでなく、神社のご利益を受け取れない原因になってしまうことがあります。注意しておきましょう。縁起が悪いとされる日の例は、以下の通りです。
- 不成就日
- 赤口
- 鬼宿日
- 仏滅
最も行ってはいけないのは、何をやってもうまくいくことがないといわれている不成就日です。この日に行っても出雲大社のご利益を受け取ることはできないでしょう。また、鬼が出る赤口や鬼宿日も避けた方が無難です。仏滅は気になるならやめておく程度で構いません。
神社にお参りしてはいけない日については、以下で詳しく紹介しているので、参考にしてくださいね。
出雲大社に呼ばれる人がいる?特徴は?

出雲大社の神様に愛され、呼ばれる人もいます。出雲大社に呼ばれる人の特徴は、以下の通りです。神様のメッセージを正しく受け取るために、よく確認しておきましょう。
- 夢で出雲大社を見る
- 出雲大社について日頃よく見聞きしている
- 出雲大社に行きたいと感じている
夢で出たり、周囲で見聞きしたりするなど、あなたの意識に出雲大社が現れたなら、神様に呼ばれているサインですよ。また、いきたいという気持ちが膨らみ切実に感じるほど、神様に呼ばれていると考えて良いです。出雲大社に足を運んでみましょう。
出雲大社に呼ばれる人について詳細を知りたい方はこちらもご覧ください。
出雲大社のタブーについて知ろう
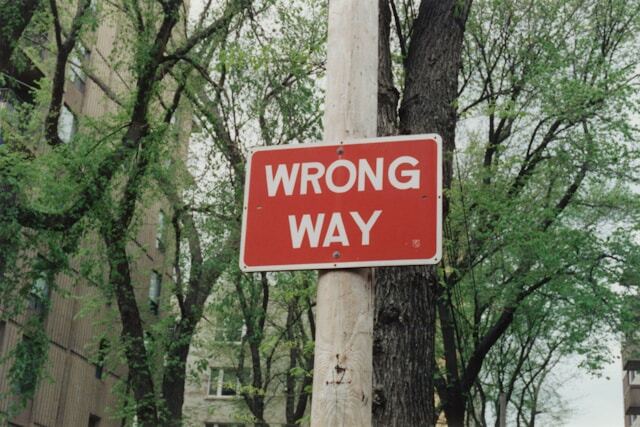
出雲大社の参拝には、6つのタブーがあります。おみくじやお賽銭に関するタブーのように他の神社と同じものもあれば、お清めの砂や鳥居についてなど、出雲大社特有のタブーもあります。知らずに神様の怒りを買わないよう、事前に知っておくことが大切です。
タブーを犯してしまうと、せっかく行ってもパワースポットである出雲大社のスピリチュアルなご利益を受けることができなくなる可能性があります。ぜひタブーを知り、マナーを守って出雲大社に参拝してくださいね。
![Callat media[カラットメディア]](/assets/logo-575bce10aaa5b85f43a2f4b11f35247844b90e465414280f4564ac5cabaa81dd.png)


公式HP ブログ Instagram YouTube
ヒーラー育成講師
過去の深く傷つく出来事がきっかけで14年間鬱病を患い精神科通いの日々を送っていたが、レムリアン・ヒーリング...
公式HP ブログ Instagram YouTube
ヒーラー育成講師
過去の深く傷つく出来事がきっかけで14年間鬱病を患い精神科通いの日々を送っていたが、レムリアン・ヒーリング®︎との出会いで人生が一変。 親しみやすいブログは読むだけで癒されると人気になり月間2万アクセス超となる。 丁寧で親身なセッションや講座が定評で、受けることで人生がポジティブに変わる人が続出している。 現在は人を癒す使命がある方の眠っている能力を開花させ、使命を全うして豊かで幸せになっていただくことをモットーにセッション・講座を提供している。
保有資格:レムリアン・ヒーリング®️認定ティーチャー現代霊気ヒーリング協会公認 マスター(師範)